
地に根ざすかのように、プリミティブで力強い。それでいて普段の生活になじむシンプルでモダンなうつわ。それが陶芸作家・野口 悦士(のぐち えつじ)さんの作品です。
陶芸を志して種子島に渡り、唐津・アメリカ・デンマークなどでの滞在制作を経て、現在は鹿児島を拠点に活動しています。
野口さんが現在のうつわの表現にたどり着くまでには、どんなストーリーがあったのでしょうか? ルーツやインスピレーションの源について、本日より全4話でお届けします。
第1話では陶芸との出会いから、師匠である中里 隆(なかざと たかし)さんに教わった、うつわの在りかたについてお話をうかがいました。
直感で決意した種子島への移住
野口さんが大学時代に何よりも夢中になっていたのがサーフィンでした。陶芸家を志す兆しとなった、手仕事への興味が芽生えたのもこのときです。
「サーフィンの虜になっていくうちに、サーフボードの構造やつくりかたに興味が湧いて、茅ヶ崎の工房でアルバイトをはじめました。
サーフボードってものすごく繊細で、最後は一つひとつ人の手で仕上げるんです。職人さんによって個性がでるのも魅力に感じました」
大学卒業後、そのままサーフボードの職人になることも考えたものの、早々に断念したといいます。
「サーフボードは一般的にポリウレタンを成型してから、グラスファイバーで固めていきます。
バリ(毛羽立ったように細かく不要な突起)をサンダーで削っていくときに出る、粉塵や臭いがすごくて。防塵マスクをしても化学物質を吸い込むことは完全に防げないため、健康に支障をきたしてしまうこともあるんです。
サーフィンもサーフボードをつくることも好きではありましたが、一生続けていく仕事としては不安がありました」
大学卒業後、就職した会社を1ヶ月で辞めてしまった野口さん。これからどうやって生きていこうか悩んでいたとき、たまたま手にした1冊の本が人生を変えることになりました。
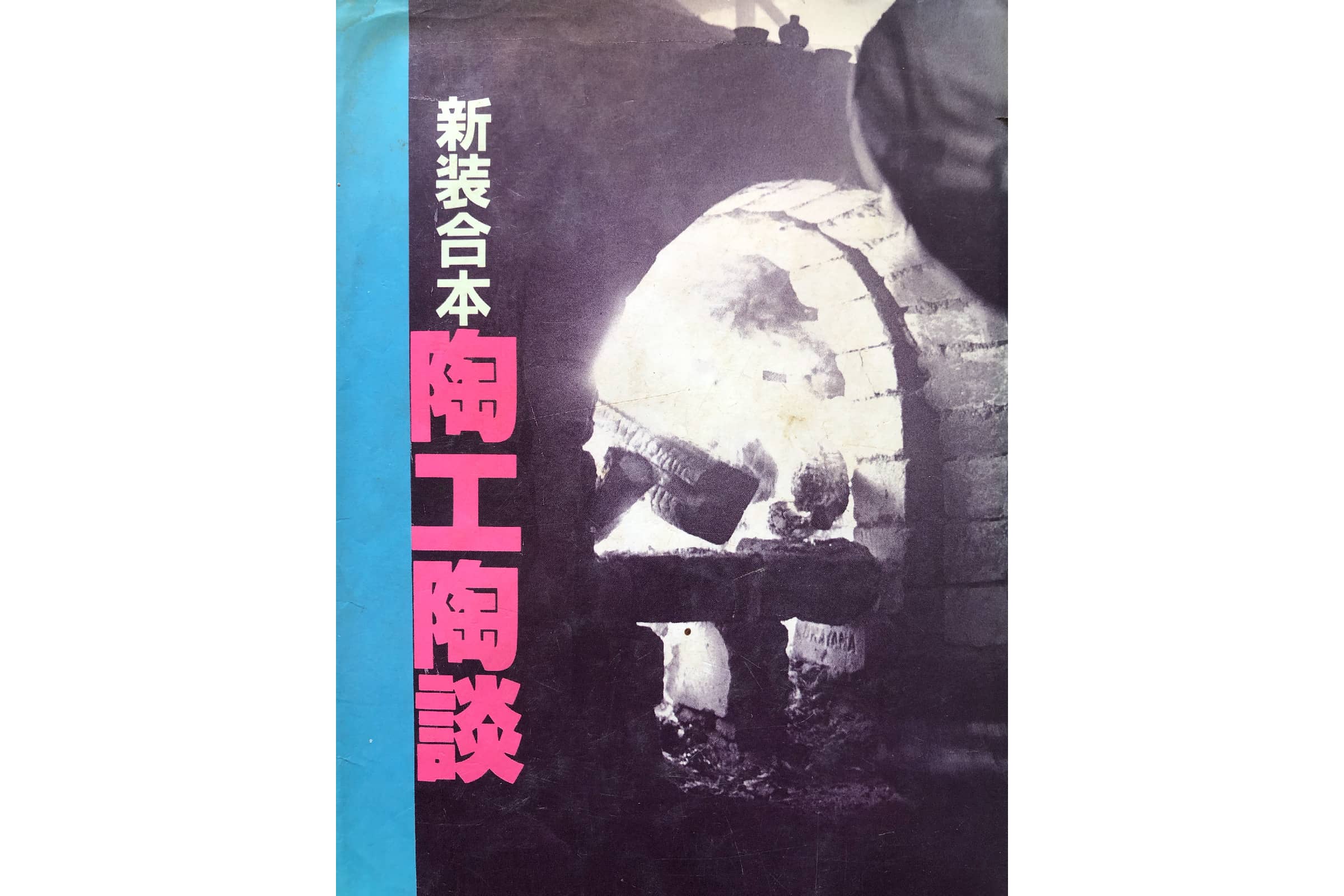 「この時期は毎日のように図書館に通っていました。そこでたまたま、日本全国の窯元や陶芸家にインタビューをしている本を見つけたんです。
「この時期は毎日のように図書館に通っていました。そこでたまたま、日本全国の窯元や陶芸家にインタビューをしている本を見つけたんです。
当時、陶芸のことは全くわかりませんでした。なんとなく『土っていいな』と思いながらページをめくっていくと、最後のほうに種子島の焼き物が紹介されていて。そこに載っていた、素朴で力強いうつわを一目見て、直感的に惹かれました」
それはのちに、野口さんの師匠となる陶芸家・中里 隆(なかざと たかし)さんの作品でした。中里さんは、唐津焼の人間国宝・中里 無庵(なかざと むあん)の家に生まれ、現代の唐津焼作家を代表する一人です。
独特な存在感を放つうつわは、日本だけでなく世界でも人気を集めています。種子島で作陶していた時期もあり、種子島焼の現在のスタイルを最初に確立したのも中里さんでした。
それにしても、全国の窯元のなかからなぜ種子島に惹かれたのでしょうか。
「中里さんの作品に心奪われたのが大きくて。それに『種子島だったら陶芸をしながらサーフィンもできるんじゃないか』と軽い気持ちで決めていましたね」
種子島の人々の優しさに触れて
サーフィンと陶芸が結びつき、種子島への移住に踏み切った野口さん。1999年、大学を卒業したばかりの23歳で島に渡ったものの、住むところも決まっていない状態でした。
「時間はあるけどお金はないという状況だったんです。なのでまずはキャンプ場に泊まることにしました。ところがその日のお客さんが僕だけで、管理人さんが管理人室に布団を敷いてくれて『今日はここで寝なさい』と。
夜になったら彼の奥さんがご飯と焼酎を持ってきてくれて、翌日には軽トラックも貸してくれて。都会では得られないような島の人たちの優しさに触れて、種子島での生活が始まりました」
その後も周りに助けられながら、いつの間にか念願だった陶芸にもとりかかれることに。しかし憧れの中里さんには出会うこともなく、時間だけが過ぎていきました。
「最初は、見よう見まねで練習をしていました。ほば独学でしたね。だからどうしても基礎が足りなくて、中里先生のもとで勉強したいという気持ちがどんどん強くなっていっていきました」
窯を焚き、土に触れるたび、陶芸の世界にのめり込んでいく野口さん。当初は毎日のように通っていた海やサーフィンからもだんだん足が遠のき、作陶に没頭していきます。そして移住をしてから3年ほど経ったころ、ついに中里さんに手紙を送るのでした。
「先生がテレビや雑誌に出ると、必ず種子島のことに触れていたので、思い入れがあることは知っていました。
だから『僕はいま26歳で、種子島で陶芸をやっていきたいと思っています』と書けば、まあ無視はされないだろうと。
それで手紙は受け取ってくれたんですが、電話がかかってきて、『もう弟子をとらないよ』とさらっと断られてしまって……。だけど『一度遊びに来てみたら?』と先生が暮らす唐津に招いてくれたんです」
すぐに中里さんの元を訪ねた野口さん。4、5日間窯の仕事を手伝いながら、夕方のほんの30分ほど、基礎的なろくろの引きかたなどを中里さんに教わることができたのです。
ゆっくりと育まれた師弟関係
 中里さんとともに過ごし、わずかながら指導も受けることができて感動もひとしおかと思いきや、野口さんの胸中は苦しいものでした。
中里さんとともに過ごし、わずかながら指導も受けることができて感動もひとしおかと思いきや、野口さんの胸中は苦しいものでした。
「『弟子をとらない』と言われたことへのショックもあったんですけど、そのときの僕があまりにもできないというか…、教えていただいた基礎すら満足にできなくて。先生のレベルに到達するまで、この道は果てしないなと、すごく打ちひしがれたことを覚えています。
『種子島でやれているつもりでいたけど、3年間僕はなにをやっていたんだろう』みたいな。まあ世間を知ったのかもしれませんね」
挫折を種子島に持ち帰った野口さん。中里さんのもとで陶芸を学ぶ道は絶たれたかに思えましたが、しばらく経った頃に中里さんから連絡がきたのでした。
「『窯焚きをするから唐津に来ませんか?』と、先生の息子さんの太亀(たき)さんが連絡をくださって、年に1〜2回唐津に行き1週間ほどお手伝いをする関係になっていました。種子島に帰ってからは、先生から教わったことをひたすら練習していましたね」
ゆっくりと、しかし確実につかみとった縁。その関係が何年か続いた2006年に、中里さんが古希(70歳)の記念に大きな展覧会を開くことになり、さらに距離が近づきます。
「先生は種子島のことをすごく大事にしていたので『種子島で作陶したい』と僕に声かけてくださったんです。もちろん大歓迎ですよね。
そのときに、僕がつくってきたうつわを認めてくださって。とても嬉しかったことを覚えています」
助手として中里さんと一緒に生活をし距離が縮まったことで、作陶の時間以外からも、うつわづくりへの姿勢を知るようになりました。
食事とうつわ、用の美
 ▲中里さんとアメリカへ
▲中里さんとアメリカへ
古希の個展を機に、野口さんは中里さんの仕事に同行する機会が増えました。アメリカ・コロラド州での制作では、仕事の傍ら弟子として学ばせてもらえることに。ここでの経験を経て、野口さんの作品には大きな変化があったといいます。
「アメリカに行って特に新鮮だったのは『こうしなきゃいけない』という決まりがないことです。
向こうの人は『同じゴールにたどり着くなら、その過程は自由に試してみる』という、セオリーにとらわれない感覚を持っていて、すごく面白いなと思いました」
コロラドに滞在していた2ヶ月間、アメリカの自由で合理的な気質を肌で感じる一方で、中里さんとの生活は実に日本らしく、もてなしの精神に溢れたものでした。
「日本にいたときと同じように、先生はアメリカでも頻繁にお客さんを呼んでいました。朝ご飯のときの話題が『今日の夜は、お客さんと何を食べようか?』なんですよ。
『いい魚が手に入ったから、僕が捌くあいだ野口くんは野菜を干しておいて』って。陶芸よりも人招くほうがメインで、食材の仕入れや仕込みの合間にろくろを回すような日々でした」
まず暮らすことが中心で、その一部に仕事がある。作陶に没頭するのではなく、現地の人々と交流することを大切にする中里さんの人となりに、さらに魅力を感じたそう。
「お客さんはアメリカのかたなので、日本料理を出すとすごく喜ばれるんです。先生もそれを知っているから、スーツケースには自分の服より、だしの材料や味噌などの食材をたくさん持ってきていて。
野菜や魚は現地で調達しますが、コロラドには海が近くにありませんでした。なので、日本料理店のかたと仲良くなって分けてもらうことも。
毎朝おかゆと味噌汁と漬物と納豆と冷奴とみたいな食事だったので、たまには『マフィンとか食べたい』と思うくらい和食漬けの日々でした」
 誰かと食事を楽しむために、自分のうつわがある。中里さんとのコミュニケーションを通して、うつわは「つくるだけ」では完成しないということを知ります。
誰かと食事を楽しむために、自分のうつわがある。中里さんとのコミュニケーションを通して、うつわは「つくるだけ」では完成しないということを知ります。
「先生のうつわは、料理を盛り付けて完成するんです。例えば出汁を引いて、湯がいた青菜をさっと盛るだけでかっこいい。
うつわもよく見えるし、もちろん料理もよく見える。シンプルなんですけど、料理とうつわがお互いを引き立てあっています」
中里さんと時間を共にすることで学んだ、食卓をより豊かにしてくれるうつわのありかた。これはいまの野口さんの作風にも引き継がれています。
次回は、中里さんと同じく野口さんの作品に大きな影響を与えた、デンマークのKH Würtz(コーホーヴューツ)についてお話をうかがいます。
(つづく)

野口 悦士(のぐち えつじ)
1975年、埼玉県生まれ。陶芸を志して種子島に渡り、アメリカ・デンマークなどでの滞在制作を経て、現在は鹿児島に拠点を置く。2006年より中里 隆氏に師事。2018年にデンマークのKH Würtzにて薪窯築窯。土と釉薬、焼成を巧み扱い、プリミティブで力強く、モダンな存在感を放つうつわをつくり続けている。
https://etsuji-noguchi.com/
野口悦士 作品展 Sight the Soil
会場:doinel (ドワネル) 東京都港区北青山 3-2-9
会期:2021年 7月 30日(金) – 8月 10日(火)
営業時間:12:00 – 19:00 水曜定休
◯状況により整理券配布、または入店をお待ちいただく可能性もございます。
◯会期の途中より、一部 online store でも展開予定です。
Interview with Etsuji Noguchi
(1) 陶芸家を目指して種子島へ
(2) 40歳。人生の転機とデンマーク
(3) 削ぎ落とされた「土と釉薬」の選択肢
(4) 新しい可能性を探る、野口悦士の現在地とは?
≫ story TOPページ
https://doinel.net/journal/category/story
Photo credits:Etsuji Noguchi(1枚目をのぞく)
Writing:Yukari Yamada
Interviewer & Edit:Yuki Akase
